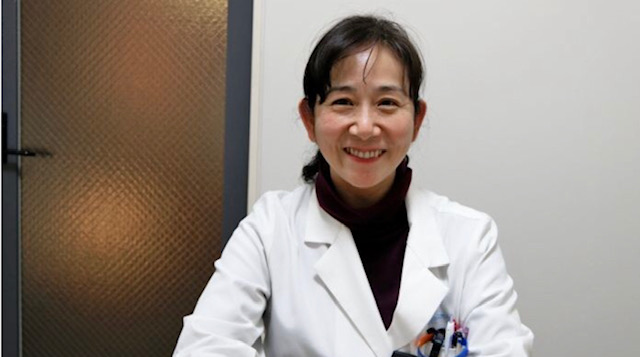<「死」がゴール 麻酔科医から看取り医に転身した訳>
『おかやま在宅クリニック』院長、岡山容子先生。訪問診療医として地域に根差す”看取り医”に努めておいでです。常時70名ほどの患者さんを担当し、ご家族や在宅ケアスタッフと共に“旅立ち”に向けたサポート。その思いやご活動はご著書『それでも病院で死にますか』にまとめられ上梓されています。まずは前身となる麻酔科医の時代を振り返りつつ、訪問診療医へと転身した道のりを伺います。
岡山容子(おかやま・ようこ) /筆名・尾崎容子(おかざき・ようこ)
訪問診療医。『おかやま在宅クリニック』(京都市中京区)院長。1971年、大阪府に生まれる。京都府立医科大学卒業。京都府立医科大学麻酔科学教室、集中治療室、西陣病院(京都市上京区)麻酔科勤務を経て、2013 年、千春会病院(長岡京市)在宅医療部に勤務。2015年、京都市中京区に在宅療養支援診療所「おかやま在宅クリニック」を開業。2018年より、産経新聞大阪本社地域版(中国四国、京都、兵庫、和歌山、三重、福井)にて「在宅善哉」を月2回連載中。2019年11月『それでも病院で死にますか』(セブン&アイ出版)を上梓。2020年12月講談社ビーシーより『それでも病院で死にますか』オンデマンド(ペーパーバック)版(税込1760円)を出版。
(本文)
それでも病院で死にますか 常に「死」を意識してきた子ども時代
岡山先生が在宅療養支援診療所『おかやま在宅クリニック』(京都市中京区)を開業されたのは2015年のこと。それまでは同じく京都市内の病院で麻酔科医としてご勤務。その麻酔科医となったのもやがて終末期医療に携わりたいという一願があってのことでした。
――京都府立医科大学の学生時代から”看取り医”志望だったそうですね
医師となった自分がやるべきことを考えた際、「私が治す!」という根治に情熱を注ぐことよりも死を目の前にした人の苦しみをとる医師になりたいと考えたんですね。
拙著『それでも病院で死にますか』のあとがきにも記しておりますが、私はもともと医師が嫌いでした。私が知る限り、不愛想で偉そう、そんなイメージが強くて好きになれなかったんです。
では、どうして医学部進学したかというと浪人生時代の学生さんたちがきっかけでした。医学部志望の学生の中に地方出身者をバカにしたり、人を成績で判断をする態度をとったりする人たちがいました。「こんな人たちが医者になる。私はこの人たちに診察されたくない」と憤慨したんです。今は若気の至りだったと思うのですが。
医大で学びながら、自分自身ならば、どんな医師の治療を受けたいか、死にゆく時をどのように迎えたいかを考えました。そして医師であるのならば、死にゆく患者さんに最後まで寄り添いたいと思いました。治療ではないターミナルケアにまず興味を持ったのが学生時代のことでした。そこでまずは痛みの専門である麻酔科に進みました。当時はまだ在宅医療という概念がなかった頃のことです。
――早い段階からお看取りを志望されたということですね。とはいえ、すべての医師が「死」に慣れているわけではない、というお話しも伺いますが
麻酔科の先輩や同僚たちの中には、終末期も緩和ケアも嫌だっておっしゃる先生もいらっしゃいました。一方で緩和ケアをしたくて麻酔科に入ってきた私のような人間も少なからずいたんですね。
そもそも私自身が死に対する親和性の高い子供でした。「死ぬってどういうことなの?」とか「生きるってなんだろう?」などと早くから「死」を徹底的に考えたからこそ、生きることを大切にしたいって思いました。
病院は「病を治すための箱」のようなものです。患者さんもまた病気を治して欲しいと願って通院されたり、入院されたりしています。それが終末期となると扱いが違ってきます。
院内で療養中の方を見て「あまり幸せそうじゃないなあ」と思いました。認知症の方と思われる高齢者が呼んでいるのに誰も興味を示さない。そこで尋ねたところ、「ああ、いいんです。」と。しかし、なにかを必死に訴えているのに、まるで居ないかのように扱われているのを見て「こういう医療をしたいとは思わないなあ」と感じたんです。積極的治療が終わった後の方もあまり興味を払ってもらっていないように思いました。「死ぬ前には自分だったらもっと大事にされたいなあ」と思いました。現場では死を前にした人たちがあまり大切にされているようには学生の私の目には映りませんでした。
だからこそ、どうしたら、人としてもっと大切にされながら旅立てるのかを考え終末期医療を志しました。当初は緩和治療をする科として放射線科と麻酔科で悩みました。手術室や救急室で手を動かすことを学びつつも、蘇生を施すのではなく静かに見送る医者になりたいと思って最終的には麻酔科を選びました。

『おかやま在宅クリニック』開業から5年。現在の訪問診療、訪問看護の強みを活かして治療にあたっている
死別歴、離別歴、親との同居もOKの婚活条件
――麻酔科勤務時代にご結婚されたそうですね
2003年に結婚しました。ずっと男社会で生きてきて恋人もいなかったのですが、結婚願望もあり子供も欲しかったのですが、このままなにもしなかったら結婚できないぞと考えました。ならばお見合い市場に打って出るしかないなって思ったんです。お見合いはいわばカタログショッピング。スペックが良いうちに売り出すに限ります(笑)。
――夫選びの条件はなんでしたか?
まずは仕事をする女性が嫌じゃない人。そして、勉強が好きな男性。さらに私が勉強することが嫌じゃない男性。年収格差があると不和のもとなので年収600万円以上を希望しました。外見はとくにこだわらず身長は150センチあればよし。私は当時32歳でしたが年齢も50歳以下ならよしと。
――ストライクゾーンが随分広いですね(笑)
確かに(笑)。死別歴OK、離別歴OK。親との同居OKと言ったら結婚相談会社の方がそこまで下げなくてもとおっしゃって。でも「私は『NOといえる日本人』なので、NOは私が言うから、そっちで狭めないで欲しい」とお願いしました。強いていうならタバコを吸わない人という条件は重視しました。
――それでお相手はすぐに決まったんですか?
割と早く決まりました。お見合いは土日の午前の部、午後の部と分けて、せっせと会って、さっさと決めるようにしました。そうして知り合ったのが一般企業のエンジニアだった夫です。
壮絶だった結婚生活と勤務の両立
――とはいえ、32歳というと、とてもお忙しい時期だったのではないですか?
結婚、助教就任、さらに出産と博士号の取得とおめでたいことが重なった時期ではありました。中でも出産時に産休育休っていうのが考慮されなかったのは厳しかったですね。産後、10週から復帰、出産から3ヶ月でICU当直し、復帰最初の当直で2時間の心マッサージを続けた経験があります。普通は30分程度で心マッサージは中止するものですが、ご家族に懇願されてしつづけてしまいました。
このような勤務でしたので勿論、夫にも無理を強いることになってしまいました。出産からわずか3か月、夜中に3回授乳が必要な乳飲み子をぽいと渡された訳ですから、夫も鬱になってしまって失業。私も全身アトピーになり、目は真っ赤で視力が変わるぐらいに目が腫れ上がってしまって体力気力の限界にありました。そこで教授に「お願いですからやめさせてください」とすがって、土下座してわんわん泣きながら頼み呆れられ、なんとか大学を退職できました。
――お辛かったと思います。それでも麻酔科勤務時代にはどのような学びがありましたか?
ホスピス(緩和ケア病棟)で研修を受けている際、「在宅ホスピス」という新しい取り組みがあることを知りました。患者さんのご自宅で緩和ケアを含めたホスピス的な療養ができるのです。実際に見学してみるとまず患者さんの表情が違うことに気づきました。
――どのような違いですか?
まず表情ですね。入院されている患者さんよりもずっと表情が穏やか。在宅ホスピスならば、がんの末期状態だけでなく、認知症や老衰の患者さんなども、ご家族と一緒に住み慣れた家で人生の最後を見守ることができるのではないかと考え、在宅医療に転向しました。
――こうしてやっとたどり着いた在宅医療への道。次回は、岡山先生の在宅医療の在り方、ご著書『それでも病院で死にますか』について伺います。
文:泉美咲月